第25回日本認知療法・認知行動療法学会では、様々なカテゴリーにおいて、必要な基礎知識の普及と情報の共有を目的とした「ワークショップ」を開催いたします。
このプログラムには分野を問わず多くの方々にご参加いただきたくご案内をいたします。
日本認知療法・認知行動療法学会の会員でない方、また第25回日本認知療法・認知行動療法学会には参加しない方も受講料をお支払いいただければ、受講が可能ですので、詳しいお手続きは本会HP「参加登録」をご確認ください。
定員に達し次第、締め切りとさせていただきます。

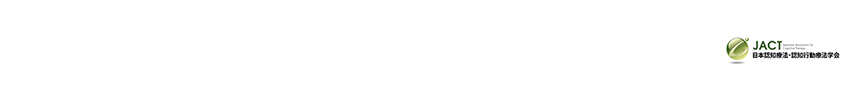
ワークショップ
ワークショップ1
動画やウェブサイトを用いて短い時間でも行える効率型CBT
11月16日(日)9:00-12:00 第1会場
- オーガナイザー・講師:
- 久我 弘典(国立精神・神経医療研究センター 認知行動療法センター)
- オーガナイザー・講師:
- 梅本 育恵(国立精神・神経医療研究センター)
- オーガナイザー・講師:
- 徳山 明広(ハートランドしぎさん)
- 講師:
- 三田村 康衣(国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 認知行動療法センター 研修指導部)
- ファシリテーター:
- 山本 洋美(国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター)
- ファシリテーター:
- 浜村 俊傑(国立精神・神経医療研究センター 認知行動療法センター)
- ファシリテーター:
- 牧野 みゆき(国立精神・神経医療研究センター 認知行動療法センター)
- ファシリテーター:
- 駒沢 あさみ(国立精神・神経医療研究センター 認知行動療法センター、目白大学)
主旨・狙い
本ワークショップでは、限られた時間でも施行できる
SCBT(Streamlined Cognitive Behavioral Therapy;効率 型認知行動療法)で用いるウェブサイト、
動画等を用いて、20分前後で行う短時間のCBTについて紹介します。
CBTを行いたいが、50分もの時間を取ることが難しいと諦めている臨床家の皆様に、
短時間で行うSCBTを体験して、日々の臨床の中で取り入れるヒントを得ていただきたいです。
実際にウェブサイトを使用してみますので、可能な方はPCやスマートフォンなどをお持ちください。
参加者の皆様には、すぐに使えるSCBTのマテリアルをパウチして差し上げます。
本ワークショップは、令和4年度厚生労働科学研究費補助金
「認知行動療法の技法を用いた効率的な精神療法の 施行と普及および体制構築に向けた研究
(課題番号20GC1016 代表:久我弘典)」
において開発された成果物を使用します。
SCBT(Streamlined Cognitive Behavioral Therapy;効率 型認知行動療法)で用いるウェブサイト、
動画等を用いて、20分前後で行う短時間のCBTについて紹介します。
CBTを行いたいが、50分もの時間を取ることが難しいと諦めている臨床家の皆様に、
短時間で行うSCBTを体験して、日々の臨床の中で取り入れるヒントを得ていただきたいです。
実際にウェブサイトを使用してみますので、可能な方はPCやスマートフォンなどをお持ちください。
参加者の皆様には、すぐに使えるSCBTのマテリアルをパウチして差し上げます。
本ワークショップは、令和4年度厚生労働科学研究費補助金
「認知行動療法の技法を用いた効率的な精神療法の 施行と普及および体制構築に向けた研究
(課題番号20GC1016 代表:久我弘典)」
において開発された成果物を使用します。
参考資料:認知行動療法マップ
ワークショップ2
心理ネットワークアプローチ
11月16日(日)9:00-12:00 第2会場
- オーガナイザー・講師:
- 国里 愛彦(専修大学 人間科学部 心理学科)
主旨・狙い
認知行動療法におけるケースフォーミュレーションは、環境・認知・感情・行動・身体の悪循環として記述される。認知行動療法の実践においては、これらの変数間の相互作用や循環はごく自然に理解されるが、研究上このような変数間の関係性を扱う方法は多くなかった。しかし、近年は心理ネットワークアプローチが提案され、心理変数間の関係性をネットワークの形で可視化するという方法が簡易に使えるようになってきている。現状において、心理ネットワークアプローチは学術研究で用いられる解析手法として扱われているがあるが、単一事例においても適用可能な解析手法であり、私達が認知行動療法を実践する際のケースフォーミュレーションや患者の状態理解においても利用可能な手法となる。また、新たな認知行動療法の枠組みとして提案されているプロセス・ベースド・セラピーでは心理的変数の関係性をネットワークで図示するが、このアプローチは心理ネットワークアプローチと親和的である。このように、心理ネットワークの考え方や解析手法は今後の認知行動療法の実践の中でも活用されることが予想される。しかし、心理ネットワークアプローチにおいてはRなどの統計解析ソフトを使うこともあり、臨床家が日々の実践において扱いやすいものではないかもしれない。本ワークショップでは、心理ネットワークアプローチについてわかりやすく解説するとともに、明日からでも心理ネットワークアプローチが実施できるようにRを用いた解析法についても解説する。統計解析ソフトRを使ったことがない方にとっては敷居が高いと感じるかもしれないが、初めてRに触れる方も参加しやすいように工夫してワークショップを実施予定である。
実際にRを動かして心理ネットワークを学ばれたい場合は、会場にノートパソコンをお持ちになってください。
ワークショップ3
トラウマ課題を持つ人々へのCBTの適用:トラウマ専門治療の前に出来ること
11月16日(日)9:00-12:00 第3会場
- オーガナイザー:
- 松本 和紀(こころのクリニックOASIS)
- オーガナイザー:
- 佐藤 秀樹(福島県立医科大学)
- 講師:
- 大澤 智子(兵庫県こころのケアセンター)
主旨・狙い
2024年度に心的外傷に起因する症状を有する患者に対する心理支援が診療報酬化された。加えて,ICD-11により複雑性PTSDや遷延性悲嘆など,トラウマの視点から重要なカテゴリ診断が準備されてきたことから,トラウマに対する臨床実践を要請される機会が増えている。そこで本ワークショップでは,主に認知行動療法に馴染みはあるがトラウマ領域については少し自信がもてないという支援者を想定し,そうした方々にトラウマ領域に関心をもってもらい,トラウマの課題を持つ人々に認知行動的技法を適応していくための導入となる実践的な知識とスキルを習得することを目指す。
ワークショップ4
教育・特別支援分野でのエビデンスベイスト・プラクティス
11月16日(日)9:00-12:00 第4会場
- オーガナイザー:
- 小関 俊祐(桜美林大学 心理・教育学系)
- 講師:
- 戸ヶ﨑 泰子(宮崎大学大学院教育学研究科 教職実践開発専攻)
主旨・狙い
近年、児童生徒の生徒指導上の諸問題は深刻化しており、国は「誰一人取り残されない学びの保障」を目指して様々な施策を展開しています。例えば、不登校対策(COCOLOプラン)では、「心の小さなSOSを見逃さずに「チーム学校」で支援すること」や「学校の風土の「見える化」を通して、 学校を安心して学べる場所にすること」など、学校・学級へのアクセスを高めるための提言がなされています。また「不登校の児童生徒の学びの場の確保策」も講じられています。こうした取り組みを形骸化せず、実効性のあるものにするためには、早期発見・早期対応の具体化、専門職との連携体制の構築が不可欠です。教育現場における認知行動療法(CBT)は、このようなニーズに応えうる有効なアプローチの1つです。
本ワークショップでは、教育・特別支援分野におけるCBTの理論と技法を概説した後、スクールカウンセラー(SC)等の専門職や学校教員としてCBTをどのように教育相談場面や教育現場でどのようにCBTを活用することができるかを演習形式で学んでいきます。具体的には、①実態把握のための機能的アセスメント、②支援方略としてのCBTの活用、③CBTを児童生徒に適用する際のコツ、④包摂的な学校・学級づくりなど、教育関係者、公認心理師などの皆様にとって、明日からの実践に役立つ内容を取り上げます。
本ワークショップでは、教育・特別支援分野におけるCBTの理論と技法を概説した後、スクールカウンセラー(SC)等の専門職や学校教員としてCBTをどのように教育相談場面や教育現場でどのようにCBTを活用することができるかを演習形式で学んでいきます。具体的には、①実態把握のための機能的アセスメント、②支援方略としてのCBTの活用、③CBTを児童生徒に適用する際のコツ、④包摂的な学校・学級づくりなど、教育関係者、公認心理師などの皆様にとって、明日からの実践に役立つ内容を取り上げます。
【参考文献】一般社団法人公認心理師の会 教育・特別支援部会(2024).事例で学ぶ教育・特別支援のエビデンスベイスト・プラクティス 金剛出版
ワークショップ5
メタ認知トレーニングの最前線
11月16日(日)9:00-12:00 第5会場
- オーガナイザー・司会:
- 石垣 琢麿(東京大学 大学院総合文化研究科)
- 講師:
- 田上 博喜(宮崎大学医学部 看護学科 生活・基盤看護科学講座)
- 講師:
- 石川 亮太郎(大正大学 臨床心理学部 臨床心理学科)
主旨・狙い
精神症状に関連する認知バイアスに気づき、自ら修正するためのメタ認知トレーニング(MCT)は、日本でもすでに多くの医療機関で実践されており、一般社団法人MCT-Jネットワーク(https://mct-j.jpn.org/)の入会希望者も増え続けている。一方、MCT開発者のモリッツ教授が率いるハンブルク大学の研究室では、MCTの適応範囲を次々と広げ、新たに多くのツールや介入法が開発されている。今回のワークショップではMCTの最前線を紹介し、日本の日常臨床に活かす方法を参加者と一緒に考えたい。
ワークショップの最初に、MCTの実践経験が少ない参加者のために、MCTの基本的考え方やツールを概説する。次に、新しいツール/介入法として、急性期入院患者のためのMCT-Acute、高齢うつ病患者のためのMCT-Silver、スマートフォンで使用できるMCTアプリCOGITO、身体集中反復行動へのアプローチを紹介する。それぞれの日本語版スライド、アプリ、動画を使って、実際に参加者に体験していただく。最後に、MCTの効果を調べるために有益な自記式尺度等について概説する。
1.MCTの概要説明(石垣)
2.急性期入院患者用「MCT-Acute」と高齢うつ病患者用「MCT-Silver」の紹介(石垣)
3.個人のニーズに合わせたMCTの提供(MCTのアプリ「COGITO」と個人用「MCT+」の活用)(田上)
4.身体集中反復行動(BFRB)へのアプローチ(石川)
5.MCTで用いる自記式尺度の紹介(石垣)
ワークショップの最初に、MCTの実践経験が少ない参加者のために、MCTの基本的考え方やツールを概説する。次に、新しいツール/介入法として、急性期入院患者のためのMCT-Acute、高齢うつ病患者のためのMCT-Silver、スマートフォンで使用できるMCTアプリCOGITO、身体集中反復行動へのアプローチを紹介する。それぞれの日本語版スライド、アプリ、動画を使って、実際に参加者に体験していただく。最後に、MCTの効果を調べるために有益な自記式尺度等について概説する。
1.MCTの概要説明(石垣)
2.急性期入院患者用「MCT-Acute」と高齢うつ病患者用「MCT-Silver」の紹介(石垣)
3.個人のニーズに合わせたMCTの提供(MCTのアプリ「COGITO」と個人用「MCT+」の活用)(田上)
4.身体集中反復行動(BFRB)へのアプローチ(石川)
5.MCTで用いる自記式尺度の紹介(石垣)
●参加者の条件
初心者から参加可能だが、MCTの実践経験があると理解が深まると思われる。
ワークショップ6
マインドフルネス認知療法
―理論と実践の両面からアプローチし、瞑想のインストラクションも体験してみよう―
11月16日(日)13:00-16:00 第1会場
- オーガナイザー・講師:
- 佐渡 充洋(慶應義塾大学保健管理センター)
- 講師:
- 朴 順禮(慶應義塾大学 看護医療学部)
- 講師:
- 永岡 麻貴(慶應義塾大学 マインドフルネス&ストレス研究センター)
- 講師:
- 佐々木 洋平(武蔵野大学 人間科学部 人間科学科)
- 講師:
- 後藤 菜穂(慶應義塾大学 医学部精神・神経科学教室 /慶應義塾大学 マインドフルネス&ストレス研究
センター /聖マリアンナ医科大学 精神療法・ストレスケアセンター)
主旨・狙い
本ワークショップは、マインドフルネス認知療法の全体像を俯瞰した上で、中核的な概念である脱中心化について、理論と実践の両面からアプローチします。
具体的には、最初にマインドフルネス認知療法の全体の構成について解説いたします。
そのあと、中盤以降のセッションに焦点を当てて、解説と体験を通して脱中心化がどのように進んでいくか理解を深めていきます。また瞑想のインストラクションを体験していただく機会も作る予定です(スクリプトを用意しますので暗記できていなくても大丈夫です)。
マインドフルネスというと、呼吸や身体の感覚に注意を向ける瞑想のイメージが強いかもしれません。しかし中盤以降では、瞑想での観察の対象を、身体の感覚から、思考や気分といったものにも移していき、これを「頭の中の現象」としてありのままに捉える練習をしていきます。そうすることでネガティブな思考が生じてもそれに巻き込まれるのではなく、客観的にありのままに捉える「脱中心化」の力を育んでいくことが可能になります。このワークショップでは、こうした思考や気分、不快な体験に対してどのように関わっていけば、不安や落ち込み、ストレスなどの不快な体験が軽減されていくか、そのメカニズムについて体験を通して理解できる構成になっています。
さらにInquiryについても解説します。Inquiryとは、参加者がその体験をセラピストとやりとりするものです。こうしたプロセスを通して、参加者は自身の体験からより深い気づきを得ていきますが、これが多くのインストラクターにとって難しいものであるのも事実です。今回は、Inquiryの要点について説明したあと、実際のやり取りの事例を提示し、その実際について学んでいただく予定です。
具体的には、最初にマインドフルネス認知療法の全体の構成について解説いたします。
そのあと、中盤以降のセッションに焦点を当てて、解説と体験を通して脱中心化がどのように進んでいくか理解を深めていきます。また瞑想のインストラクションを体験していただく機会も作る予定です(スクリプトを用意しますので暗記できていなくても大丈夫です)。
マインドフルネスというと、呼吸や身体の感覚に注意を向ける瞑想のイメージが強いかもしれません。しかし中盤以降では、瞑想での観察の対象を、身体の感覚から、思考や気分といったものにも移していき、これを「頭の中の現象」としてありのままに捉える練習をしていきます。そうすることでネガティブな思考が生じてもそれに巻き込まれるのではなく、客観的にありのままに捉える「脱中心化」の力を育んでいくことが可能になります。このワークショップでは、こうした思考や気分、不快な体験に対してどのように関わっていけば、不安や落ち込み、ストレスなどの不快な体験が軽減されていくか、そのメカニズムについて体験を通して理解できる構成になっています。
さらにInquiryについても解説します。Inquiryとは、参加者がその体験をセラピストとやりとりするものです。こうしたプロセスを通して、参加者は自身の体験からより深い気づきを得ていきますが、これが多くのインストラクターにとって難しいものであるのも事実です。今回は、Inquiryの要点について説明したあと、実際のやり取りの事例を提示し、その実際について学んでいただく予定です。
ワークショップ7
システマティック・レビューとネットワーク・メタ分析
11月16日(日)13:00-16:00 第2会場
- オーガナイザー・司会:
- 国里 愛彦(専修大学 人間科学部 心理学科)
- 講師:
- 古川 由己(東京大学医学部附属病院 精神神経科/ミュンヘン工科大学精神科)
主旨・狙い
「認知行動療法といってもいろいろなスキルがあるけれど、結局どれが大事なの?」こんな臨床疑問を抱いたことはないだろうか。近年、このような疑問に答える研究手法が開発された。治療効果に関してエビデンスレベルが最も高いのは、ランダム化比較試験のシステマティック・レビューとメタ分析だが、その発展形として、複数の要素からなる介入について、各要素の効果を推定するコンポーネント・ネットワーク・メタ分析という手法が開発されたのだ。
本ワークショップでは、コンポーネント・ネットワーク・メタ分析を用いて不眠の認知行動療法の有効要素を検討した論文 (https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2023.5060) をJAMA Psychiatryに発表した古川先生を講師に招き、その手法の概要と研究立案時のポイントを解説いただく。不眠症以外にもうつ病、不安障害などの認知行動療法にこの手法が応用されてきているが、これらの手法が適用されていない精神障害やテーマは多い。本ワークショップを通して、参加者がコンポーネント・ネットワーク・メタ分析論文を読みこなし、さらに新たな研究知見を生み出す研究に取り組めるようになることを目指す。
なお、本ワークショップは、講師が国外にいるため、講師はオンラインでの参加となる。対面会場では司会が質疑応答やワークなどのファシリテートを行う。
本ワークショップでは、コンポーネント・ネットワーク・メタ分析を用いて不眠の認知行動療法の有効要素を検討した論文 (https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2023.5060) をJAMA Psychiatryに発表した古川先生を講師に招き、その手法の概要と研究立案時のポイントを解説いただく。不眠症以外にもうつ病、不安障害などの認知行動療法にこの手法が応用されてきているが、これらの手法が適用されていない精神障害やテーマは多い。本ワークショップを通して、参加者がコンポーネント・ネットワーク・メタ分析論文を読みこなし、さらに新たな研究知見を生み出す研究に取り組めるようになることを目指す。
なお、本ワークショップは、講師が国外にいるため、講師はオンラインでの参加となる。対面会場では司会が質疑応答やワークなどのファシリテートを行う。
ワークショップ8
がん患者さんに対する認知行動療法
11月16日(日)13:00-16:00 第3会場
- オーガナイザー・座長・講師:
- 藤澤 大介(国立がん研究センター/慶應義塾大学)
- 講師:
- 五十嵐 友里(東京家政大学/埼玉医科大学)
- 講師:
- 小川 祐子(国立がん研究センター 中央病院)
- 講師:
- 栁井 優子(国立がん研究センター 中央病院)
主旨・狙い
日本サイコオンコロジー学会と共同ワークショップです。
国民の2人に1人が罹患するがんは、様々な症状をもたらし、QOLを損ない、生命を脅かします。
認知行動療法はがんの患者さんの不安、抑うつ、不眠といった精神症状の緩和や、疼痛、倦怠感、呼吸苦といった身体症状の緩和に有益と考えられています。一方、がんに伴う身体的制約や、がん治療に伴う時間的制約から、認知行動療法を適用する際の実践上の工夫が求められます。
本ワークショップでは、がん医療で認知行動療法を実践するために必要なスキルセットを提供します。
1.心理療法を提供する上で必要最小限のがんおよびがん医療の基本知識
2.がん医療における認知行動療法のエビデンス (適応と限界)
3.支持・共感に代表される基本的コミュニケーション・スキル
4.認知行動療法の基本スキル
5.がん医療に頻発する精神・身体症状への認知行動療法の適用
6.時間的・身体的制約下での実践の工夫
7.効果的なチームワーク
がん医療だけでなく、さまざまな身体疾患に対するケアに応用可能と考えられます。
認知行動療法はがんの患者さんの不安、抑うつ、不眠といった精神症状の緩和や、疼痛、倦怠感、呼吸苦といった身体症状の緩和に有益と考えられています。一方、がんに伴う身体的制約や、がん治療に伴う時間的制約から、認知行動療法を適用する際の実践上の工夫が求められます。
本ワークショップでは、がん医療で認知行動療法を実践するために必要なスキルセットを提供します。
1.心理療法を提供する上で必要最小限のがんおよびがん医療の基本知識
2.がん医療における認知行動療法のエビデンス (適応と限界)
3.支持・共感に代表される基本的コミュニケーション・スキル
4.認知行動療法の基本スキル
5.がん医療に頻発する精神・身体症状への認知行動療法の適用
6.時間的・身体的制約下での実践の工夫
7.効果的なチームワーク
がん医療だけでなく、さまざまな身体疾患に対するケアに応用可能と考えられます。
ワークショップ9
小中高をシームレスにつなぐ ストレスマネジメント教育の理論と実践
11月16日(日)13:00-16:00 第4会場
- オーガナイザー・講師:
- 小関 俊祐(桜美林大学 心理・教育学系)
主旨・狙い
本ワークショップでは、小学生から高校生までの児童生徒が自分に合ったストレス対処法を考え、身につけることを目指したストレスマネジメント教育プログラムの運営方法や実施手順、実施上のポイントや留意点について紹介します。具体的には、同じ「ソーシャルスキルトレーニング」を行う場合でも、小学校低学年、高学年、中高生といった対象ごとに、どのように内容や進め方を調整するか、また指導のねらいがどのように異なるか、などについて解説します。
さらに、ストレスマネジメント教育の理論的背景や実践上のポイント、児童生徒の発達段階に応じた効果的な指導法についても紹介します。ワークショップでは、参加者自身が実際にワークシートを体験し、教育現場ですぐに活かせる具体的な指導スキルを身につける機会とします。
対象は主にスクールカウンセラーをはじめとした教育分野で活躍する心理師やその養成課程にある学生、教職員の方々です。ストレスマネジメント教育を導入したいが学校との連携方法が分からない、実施にあたり何をアセスメントし、どのような目的でプログラムを選択、実施すればよいのか困っている、などといった実践上の課題を抱える方々にとって、具体的なヒントや解決策を得られる機会となることを目指しています。
さらに、ストレスマネジメント教育の理論的背景や実践上のポイント、児童生徒の発達段階に応じた効果的な指導法についても紹介します。ワークショップでは、参加者自身が実際にワークシートを体験し、教育現場ですぐに活かせる具体的な指導スキルを身につける機会とします。
対象は主にスクールカウンセラーをはじめとした教育分野で活躍する心理師やその養成課程にある学生、教職員の方々です。ストレスマネジメント教育を導入したいが学校との連携方法が分からない、実施にあたり何をアセスメントし、どのような目的でプログラムを選択、実施すればよいのか困っている、などといった実践上の課題を抱える方々にとって、具体的なヒントや解決策を得られる機会となることを目指しています。
ワークショップ10
アクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT)入門
11月16日(日)13:00-16:00 第5会場
- オーガナイザー:
- 酒井 美枝(名古屋市立大学 大学院医学研究科 精神・認知・行動医学医学)
- 講師:
- 茂本 由紀(武庫川女子大学 心理・社会福祉学部 心理学科)
- 講師:
- 嶋 大樹(追手門学院大学 心理学部心理学科)
主旨・狙い
アクセプタンス&コミットメント・セラピー(Acceptance and Commitment Therapy: ACT)は,慢性疼痛,うつ,不安,物質依存,肥満など,幅広い症状・問題に対し,急速に多くのエビデンスが構築されてきている。本ワークショップでは,ACTに馴染みの少ない多職種への入門編として「ACTの視点」を,体験的に学べる機会を提供する。そのため,対象者は,ACTをどのように活用できるかイメージが湧かない初学者,うまく使いこなせていないと感じている中級者を主に想定する。
具体的には,ACTの基礎理論である臨床行動分析(Clinical behavior analysis)や関係フレーム理論(Relational Frame Theory; RFT)を概観し,体験的エクササイズの紹介を交えながら「心理的柔軟性(psychological flexibility)モデル」をおさらいする。さらには,各講師が各々の領域でどのようにACTを活用しているか取り上げ,受講者の臨床実践に役立てて頂ければと考えている。
具体的には,ACTの基礎理論である臨床行動分析(Clinical behavior analysis)や関係フレーム理論(Relational Frame Theory; RFT)を概観し,体験的エクササイズの紹介を交えながら「心理的柔軟性(psychological flexibility)モデル」をおさらいする。さらには,各講師が各々の領域でどのようにACTを活用しているか取り上げ,受講者の臨床実践に役立てて頂ければと考えている。